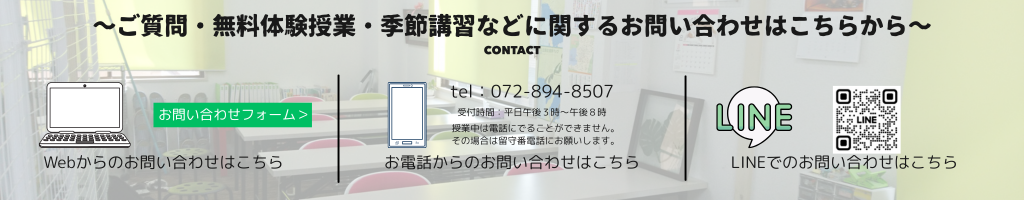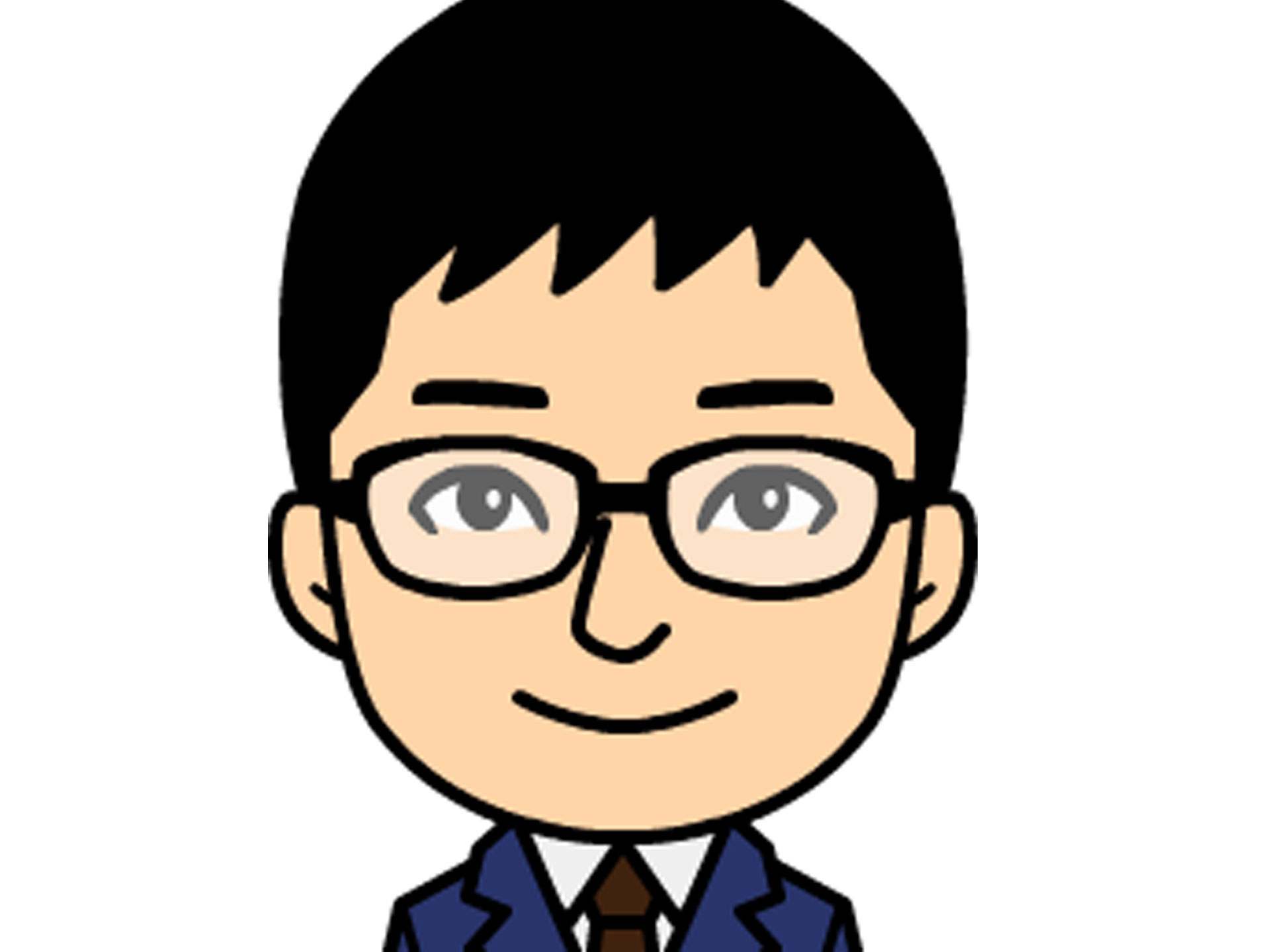はじめに
「勉強しているのに、なぜかテストで平均点に届かない…」
そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
中学生の勉強は9教科にわたります。主要5教科(国語・数学・英語・理科・社会)に加え、副教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)も内申点に直結するため、バランスよく学習する必要があります。
しかし、教科ごとに“つまずきやすいポイント”や“効果的な学習法”は違います。この記事では、保護者の方が家庭でできるサポート法を9教科別にまとめて解説します。
主要5教科編
(1) 国語
国語は「読解力がない」「漢字が覚えられない」という声が多い教科です。
つまずきやすいポイント
・問題文を最後まで読まずに答える
・漢字や語句を“その場しのぎ”で覚えてしまう
家庭でできるサポート法
① 漢字を小テスト形式で出す:親が5問だけでも出題してあげると集中力が高まります。
② 音読を一緒にする:読解問題は「問いが何を聞いているのか」を確認するだけでも正答率が上がります。
(2) 数学
数学は「計算ミス」と「文章題」が大きな壁です。
つまずきやすいポイント
・計算が正確でない
・文章題を式にできない
家庭でできるサポート法
① 正確さを優先:スピードよりも「確実に正しい答え」を出せることが大切です。
② 図を書く習慣:文章題は「図や表に整理する」練習で大きく改善します。
(3) 英語
英語は単語とリスニングで差がつきやすい教科です。
つまずきやすいポイント
・単語を“眺めるだけ”で覚えようとする
・音声を聞く習慣がない
家庭でできるサポート法
① 声に出しながら書く:書く+発音の組み合わせで記憶が定着します。
② 耳慣れを重視:英語アプリや教科書CDを繰り返し聞くことでリスニング力が伸びます。
(4) 理科
理科は暗記と実験問題の両方でつまずきやすい教科です。
つまずきやすいポイント
・用語だけを丸暗記
・グラフや図を理解していない
家庭でできるサポート法
① 「なぜそうなるのか」を問う:原因や理由とセットで覚えると忘れにくいです。
② グラフを自分で書き写す:図や表を手で再現すると理解が深まります。
(5) 社会
社会は「地理・歴史・公民の切り替え」が難しく、覚えたつもりでも忘れてしまいがちです。
つまずきやすいポイント
・地図や年表を使わず“丸暗記”
・ワークを解いて終わりにする
家庭でできるサポート法
① 教科書を音読:声に出すと頭に残りやすいです。
② 地図や年表をセットで活用:「いつ」「どこで」を意識すると知識が整理されます。
副教科編
(6) 音楽
音楽は暗記と感性の両方が問われます。
サポート法
・教科書に出てくる曲を一緒に聴いて「どう感じた?」と感想を言葉にする。
・音楽史や楽典はカード化して短時間で繰り返し。
(7) 美術
美術の評価は「丁寧さ」と「表現力」です。
サポート法
・教科書作品を見て「この絵の特徴は何だろう」と話し合う。
・絵の上手さよりも「提出物の完成度」が評価に直結。
(8) 保健体育
保健体育は暗記(保健)と実技(体育)の両面で評価されます。
サポート法
・保健は「用語をカード化して小テスト」。
・体育は「努力態度・提出物」も成績に含まれると子どもに伝える。
(9) 技術・家庭
知識と実習の両方があるため、準備不足で点を落としやすい教科です。
サポート法
・暗記はワークを穴埋め形式で繰り返す。
・実習(調理・裁縫など)は「一緒にやってみる」体験で理解を深める。
まとめ
平均点に届かないのは「才能の問題」ではありません。ほとんどの場合、勉強方法が教科に合っていないだけです。
国語は「問いを読み解く習慣」
数学は「図や表で整理」
英語は「声に出す+耳で聞く」
理科は「理由とセットで覚える」
社会は「地図・年表を活用」
副教科も「提出物・暗記・態度」がカギ
保護者の方の少しのサポートで、子どもの点数は確実に変わります。
進学塾フローライトゼミナールでは、9教科をバランスよく伸ばす指導を大切にし、「平均点を突破する学習習慣」をサポートしています。
まずは無料体験授業で、お子さんに合った学習法を体感してみませんか?